介護士とヘルパーの違いとは?仕事内容・資格・向いている人の特徴を徹底比較

介護業界で転職を考えるとき「介護士」と「ヘルパー」の違いで迷う方は多くいます。
両者は似ているようで働き方や資格の有無が異なるため、転職活動前に正しく違いを理解しておくことが大切です。
この記事では介護士とヘルパーの資格や仕事内容、向いている人の特徴を詳しく解説します。記事を読めば、介護士とヘルパーの違いが明確になり、自分に最適な進路を見つけられます。
介護士は施設でチームの一員として働き、ヘルパーは利用者の自宅で一人で対応する点が両者の大きな違いです。
それぞれの役割を深く理解し、自分の強みや希望に合った職種を選択しましょう。
介護士とヘルパーの基本的な違い
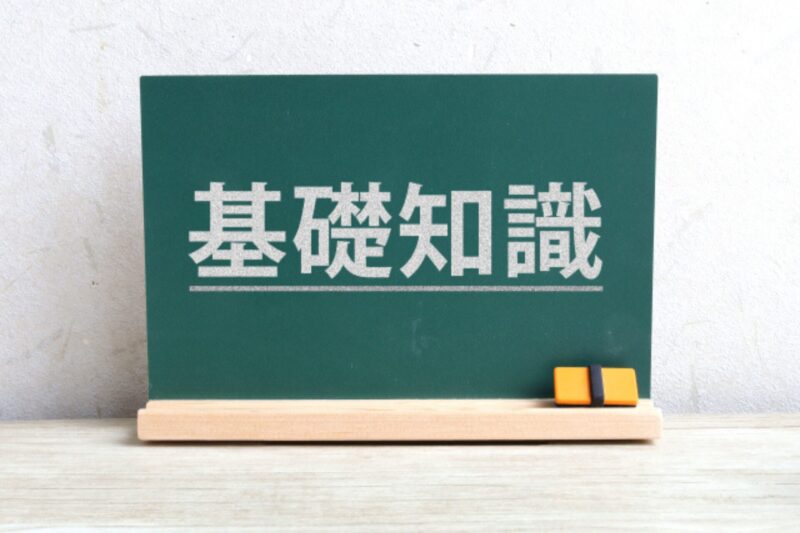
介護士とヘルパーの以下の違いについて解説します。
- 介護士とは介護の仕事をする人の総称
- ヘルパーとは高齢者の自宅を訪問して日常生活の援助を行う人
介護士とは介護の仕事をする人の総称
「介護士」の呼び名は資格を持っているかどうかにかかわらず、介護の仕事に携わる人全体の総称として使われています。
国家資格「介護福祉士」の有資格者だけでなく、資格を持たずに働いている人も介護士に含まれます。
介護士の主な勤務先は特別養護老人ホームや介護老人保健施設、デイサービスなどの介護施設です。施設で暮らす利用者の生活を支えるためのサポートが介護士の主な仕事です。
ヘルパーとは高齢者の自宅を訪問して日常生活の援助を行う人
ヘルパーの正式名称は「訪問介護員」です。高齢者や障がいを持つ人の自宅を訪問して、日常生活の援助を行う専門職がヘルパーと呼ばれています。
利用者が住み慣れた自宅で自分らしく自立した生活を続けられるための支援をすることがヘルパーの主な役割です。
ヘルパーの業務はあらかじめ作成されたケアプランに沿って行われます。ヘルパーは基本的には一人で利用者の自宅を訪問し、一対一でじっくりと向き合ったケアを行います。
介護士とヘルパーの資格の違い

介護士とヘルパーの資格要件の違いについて以下のとおり解説します。
- 介護士は資格がなくても就ける
- ヘルパーは認定資格を取得する必要がある
介護士は資格がなくても就ける
介護士は介護職の総称であり、資格がない人でも介護士になれます。無資格や未経験の人は介護士のうち「介護助手」や「介護補助」といった職種から始めることが一般的です。
無資格の介護士は以下のような利用者の体に直接触れない業務を中心に担当します。
- 食事の準備・後片付け
- 施設の清掃
- シーツ交換
- 備品の管理・補充
しかし、働く施設によっては介護士と呼ばず「ケアフレンド」など別名で呼ばれることもあります。
無資格の介護士がお風呂や着替えの手伝いといったケアをする場合は、資格を持つ職員の指示のもとで補助的に行う場合がほとんどです。
働きながら「介護職員初任者研修」などの資格取得をし、介護士としてのキャリアアップを目指すことも可能です。
ヘルパーは認定資格を取得する必要がある
ヘルパーとして働くためには国が定めた公的な資格が必要な点が、介護士との大きな違いです。ヘルパーは利用者の自宅へ一人で訪問し、現場の状況に応じた対応をします。
現場で適切な判断を下すためには専門的な知識と技術が必要なため、ヘルパーには資格の取得が義務付けられています。
ヘルパーになるためには以下の資格のうちの一つを取得しなければいけません。
- 介護職員初任者研修
- 実務者研修
- 介護福祉士
現在は廃止されている「ホームヘルパー1級・2級」や「介護職員基礎研修」の資格を取得している人もヘルパーとして働けます。
介護士とヘルパーの仕事内容の違い
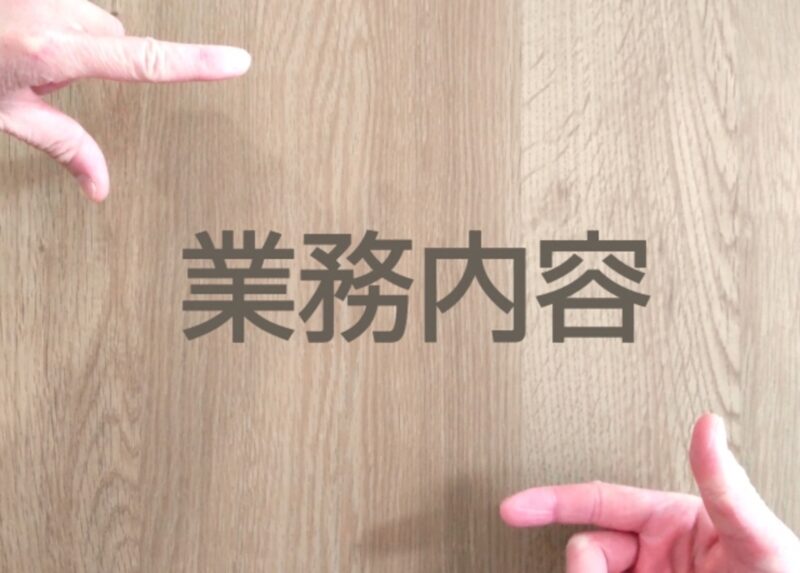
介護士とヘルパーの仕事内容の違いについて以下のとおり解説します。
- 介護士は施設で生活全般を支える
- ヘルパーは在宅生活を支援する
介護士は施設で生活全般を支える
介護士の主な仕事は特別養護老人ホームや有料老人ホームといった施設で、利用者の生活全般を支えることです。
利用者が施設の中で安全で心豊かな毎日を送れるよう、介護士は以下の幅広いサポートを行います。
- 身体介助
- レクリエーション
- 生活援助
- 健康管理
- 家族との連携
- 看取りケア
介護士は看護師やリハビリの専門家など、さまざまな職種の人たちとチームを組んで利用者の暮らしを総合的にサポートします。
ヘルパーは在宅生活を支援する
ヘルパーの主な仕事は利用者の自宅を訪問し、在宅生活が続けられるようにサポートすることです。利用者が住み慣れた家で安心して暮らせるよう、ヘルパーは以下のケアを行います。
- 食事
- 入浴
- トイレの介助
- 料理
- 掃除
- 買い物代行
- 通院の付き添い
利用者や家族とコミュニケーションをとり、不安な気持ちに寄り添うこともヘルパーの大切な仕事です。
ヘルパーは利用者一人ひとりの生活に寄り添い、在宅での暮らしを直接的に支える役割を担っています。
介護士が向いている人の特徴

介護士が向いている人の特徴は以下のとおりです。
- チームで協力して働ける人
- 体力に自信がある人
チームで協力して働ける人
チームで協力して働ける人は介護士に向いています。介護施設では一人の利用者を支えるために、看護師やリハビリの専門家など多くのスタッフがチームとして働いているからです。
チームで働くうえで、介護士には以下の姿勢が求められます。
- 適切に報告・連絡・相談をすること
- 他の人の意見を尊重すること
- 全体目標と自身の役割を理解し遂行すること
- 周囲に配慮してサポートすること
- 建設的に話し合いをすること
- トラブル対応に協力すること
体力に自信がある人
介護士の仕事は体を動かす場面が多いため、体力に自信がある人に向いています。利用者の体を支えたり、広い施設内を歩き回ったりすることが日常的に求められるからです。
介護士に体力が求められる具体的な場面は以下のとおりです。
- ベッドから車椅子への移動
- 入浴・トイレの介助
- ナースコールが鳴った際に素早く駆けつける対応
- 夜勤を含む不規則なシフトでの勤務
- レクリエーションの準備や進行といった立ち仕事
体力的な余裕は精神的な安定にもつながるため、十分な体力があれば介護士として質の高いケアが提供できます。
ヘルパーが向いている人の特徴

ヘルパーが向いている人の特徴は以下のとおりです。
- 一人で判断して行動できる人
- 礼儀正しく信頼関係を築ける人
一人で判断して行動できる人
ヘルパーは一人で利用者の自宅を訪問する業務が中心となるため、自ら考えて行動できる人に向いています。
施設での勤務とは違い、ヘルパーは周りにすぐ相談できる同僚がいない状況で勤務します。
利用者の体調が急変したり、予期せぬトラブルが起きたりした際もヘルパーは冷静に状況を判断し、対応しなければいけません。
マニュアル外のケアの選択やスケジュール管理もヘルパーが担う責任に含まれます。
ヘルパーには自律性や冷静な判断力が求められるため、一人で仕事をやり遂げることにやりがいを感じる人に適しています。
礼儀正しく信頼関係を築ける人
ヘルパーの主な勤務場所は利用者の自宅というプライベートな空間です。利用者や家族が安心してサービスを受けるためには、ヘルパーに対する信頼感が欠かせません。
礼儀正しく誠実な対応で相手に安心感を与えられる人は、ヘルパーに向いています。ヘルパーが利用者と信頼関係を築くために大切な行動や心がけは以下のとおりです。
- 基本的なマナー
- 傾聴と共感
- 時間厳守
- プライバシーの尊重
相手を尊重する姿勢と責任感のある行動はヘルパーとして活躍するための鍵です。
介護士やヘルパーに転職する際の注意点

介護士やヘルパーに転職する際の注意点として以下の3点を解説します。
- 仕事内容や勤務環境を事前に確認する
- 夜勤やシフト勤務の有無をチェックする
- 職場ごとの教育体制やサポート体制を見極める
仕事内容や勤務環境を事前に確認する
介護士やヘルパーに転職する際は仕事内容や勤務環境を事前にしっかり確認しましょう。求人票に書かれている情報だけでは、実際の職場の様子を正確に知ることは難しいからです。
面接の際に以下の点を質問してみると職場の実情を知ることができます。
- 利用者の人数・要介護度
- 身体介護と生活援助の割合
- 1日の業務スケジュール
- 職場の雰囲気・人間関係
- 残業時間・残業代
- 給与・手当・賞与
- ICT機器の導入状況
- 有給休暇・シフトの柔軟性
仕事内容や勤務環境を事前に確認すれば、介護士やヘルパーに転職する前に自分に合った働きやすい職場かどうか判断できます。
ただし、限られた時間の中で多くの情報を聞き出すのは、面接する相手も大変です。以下の記事ではスムーズに進めるコツを紹介したのでぜひ参考にしてださい。
» 介護職の転職活動を徹底解説!スムーズに進めるコツも紹介
夜勤やシフト勤務の有無をチェックする

勤務形態は給与や生活リズム、プライベート時間に直接影響を与えます。介護士やヘルパーの仕事を選ぶ前に、夜勤やシフト勤務の有無をよく確認しておきましょう。
以下の点をチェックすることがおすすめです。
- 「日勤のみ」「夜勤なし」といった求人票の情報
- 夜勤手当の金額
- 夜勤の拘束時間と休憩時間
- 早番・日勤・遅番など、シフトの具体的なパターン
- 休み希望回数の可否
- シフトの柔軟性
自分の体調や家庭の状況に合わせて、介護士やヘルパーとして無理なく働ける職場を見つけましょう。
職場ごとの教育体制やサポート体制を見極める
未経験の人や介護職のブランクがある人は、教育体制やサポート体制が整っている職場を選びましょう。
研修や相談できる環境が整っていない職場では、入職後に不安な気持ちで働くことになります。
一方、サポートが手厚い職場はスキルを身に付けながら仕事に取り組めるため、長く働き続けやすくなります。
面接や職場見学の際は以下の点を確認しましょう。
- 新人研修
- 資格取得支援
- 教育担当・メンター制度(0JT制度)
- 独り立ちまでの期間とフォロー体制
- 業務マニュアルの整備
- 職場の雰囲気
- 人員体制
介護士とヘルパーの違いに関するよくある質問

介護士とヘルパーの違いに関する以下の質問に回答します。
- 介護士とヘルパーはどちらが自分に合ってる?
- 未経験からヘルパーになることは可能?
- 介護士とヘルパーではどちらが将来性が高い?
介護士とヘルパーはどちらが自分に合っている?
介護士とヘルパーのどちらが自分に合っているかは、希望する働き方や得意な分野によって変わります。
介護施設で利用者さんと深い関わりを持ちたいなら介護士、短時間や副業など柔軟な働き方がしたいならヘルパーがおすすめです。
チームで協力して働きたい人は介護士、自分のペースで働きたい人はヘルパーが向いています。
身体的な介助が中心なら介護士、生活のサポートが中心ならヘルパーというように、仕事内容の好みに応じて選ぶことも可能です。
自分の性格やライフスタイルをじっくり考えて、より適した職種を選ぶようにしましょう。
未経験からヘルパーになることは可能?

未経験からでもヘルパーになることは可能ですが、ヘルパーとして働くには「介護職員初任者研修」などの資格が必要です。
介護職員初任者研修は学歴や実務経験に関係なく誰でも受講でき、介護の基礎知識や技術を学べます。修了までの期間はおよそ1〜6か月、費用は5万〜10万円ほどが目安です。
まずは資格がなくても働ける介護施設に勤務し、現場で経験を積みながら資格取得を目指す人もいます。
実際に働くことで介護の仕事を理解しつつ、学んだ知識や技術を現場ですぐに活かせる点が大きなメリットです。
介護施設の中には働きながら資格取得を目指せる「資格取得支援制度」を設けている事業所もあります。
資格取得支援制度では費用の一部または全額を会社が負担してくれる場合もあり、資格取得の経済的な負担を抑えられます。
介護士とヘルパーではどちらが将来性が高い?
介護士とヘルパーはどちらも将来性が高いと言えます。日本の高齢化が進むにつれて、介護を必要とする人は増え続けています。
住み慣れた自宅で介護を受けたいと望む高齢者が多いため、ヘルパーの需要は今後さらに高まる見込みです。
ヘルパーとして経験を積めば、訪問介護の計画を立てるサービス提供責任者を目指せます。将来的には自分で事業所を立ち上げてヘルパーとして独立することも可能です。
施設で働く介護士の需要も将来的になくなることはありません。介護士は施設内で経験を積むことで、チームのリーダーや施設長といった役職を目指せます。
介護士とヘルパーのどちらの職種でも、キャリアアップのためには国家資格「介護福祉士」の取得がおすすめです。
国家資格を取得すると専門性が認められ、給与や待遇の改善につながります。
介護士とヘルパーの違いを理解して自分に合った道を選ぼう

介護士とヘルパーは働く場所や資格、仕事内容などに大きな違いがあります。
介護士は施設で他の職種と連携しながら多様なケアを行う一方、ヘルパーは利用者の自宅で一対一のケアを提供します。
介護士に向いている人はチームで協力して働ける人や体力に自信がある人です。一人で判断して行動できる人や礼儀正しく信頼関係を築ける人はヘルパーに向いています。
どちらの職種に転職する場合でも、自分に合った職場を見つけるためには仕事内容や勤務環境を事前に確認しましょう。
介護士やヘルパーとしてのキャリアアップを視野に入れ、職場の教育体制やサポート体制に注目することも欠かせません。
自分のライフスタイルや価値観に合った職種を選び、介護職で長く活躍できる道を探してみてください。
-2.jpg)